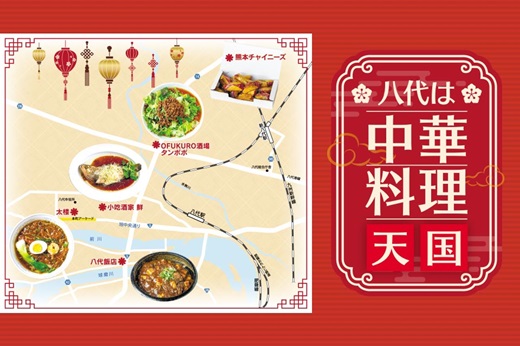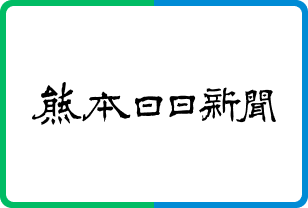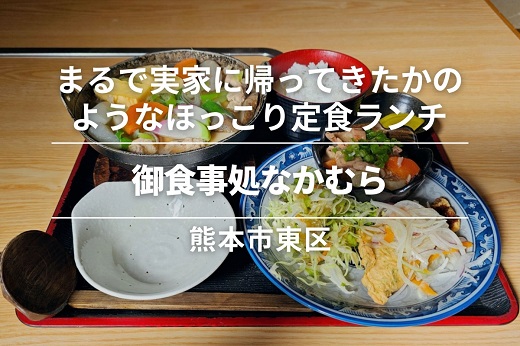「子どものため」身元調査 <ゆりかご15年>連載 第4部③

生後すぐ電話ボックスに置き去りにされたみそぎさんのように、保護者がいない子どもは児童相談所(児相)に保護される。そこで行われるのが、わずかな手がかりから身元情報を集める「社会調査」だ。慈恵病院(熊本市西区)の「こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)」に預けられ、親の身元が分からない子どもも「棄児」として扱われ、社会調査の対象となる。
通常、子どもが置き去りにされれば警察も対応する。ゆりかごへの預け入れでも保護責任者遺棄罪に当たるかどうかなどを確認し、事件性がなければ児相の調査が中心となる。
赤ちゃんがタオルケットにくるまれていれば、メーカーに販売地域を問い合わせる。「出生届が出されていないのに、おなかが小さくなった女性を見かけないか」-。全国の児相にこんな照会をかけることも。おむつが入った袋の店舗名から、預け入れた人が住む地域を特定したこともあった。
調査の対象は児相が携わる子どもや家庭全て。これらはゆりかごに関する社会調査でも変わらない。調査に携わったことがある県中央児相の隈部寛子所長(58)は「子どもには子どもの人生がある。自分がどこから来たのか答えられるように、何が何でも親の情報を探したかった」と振り返る。同児相で相談課長を務めた黒田信子さん(71)も「養親に深い愛情を受け、衣食住が恵まれればいいというわけではない。子どもは声を上げにくいが、生みの親の事情を知りたいケースは多い」と、社会調査は「出自を知る権利」のためにも不可欠だと訴える。
ただ、社会調査を行っても身元が分からない場合もある。ゆりかごに預けられた子どもは2021年度までに161人。熊本市が公表した19年度までの運用状況によると、31人は不明のままだ。熊本市児相の戸澤角充所長(53)は「預け入れた人と接触できなければ、児相ができることはないに等しい」と苦しい胸の内を打ち明ける。
社会調査で得られた情報をどのように保存し、開示していくのかという課題もある。児相の運営指針によると、児童の記録の保存期間はケースに応じて柔軟に設定するとしており、熊本市児相は、ゆりかごに関する記録を永年保存すると決めた。
ゆりかごに限れば、これまでに預けられた子どもや里親らによる開示請求は出ていない。ただ、ゆりかご事例に関わった九州のある児相の所長は、子どもが情報開示を求めた時の対応の難しさを打ち明ける。この児相では面談した際の実親の表情や発言、親の様子から職員が感じたことなどを細かく記録しているが、個人情報保護条例が壁となり、開示される情報が限定的になる可能性があるという。
所長は「国は一律的に非開示のラインを引くのではなく、子どもの知る権利を保障するため、法律の整理をしていくべきではないか」と指摘する。(「ゆりかご15年」取材班)
出自を知る権利 日本が批准する国連の「子どもの権利条約」では、できる限り父母を知る権利があると定めている。国内で規定する法律はない。ゆりかごの専門部会は昨年6月、「子どもが実の親を知る権利は保障されなければならない」として「匿名性に重きを置いたゆりかごの仕組みには限界がある」と問題提起している。
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツTHEMES
こうのとりのゆりかご-
みんなが幸せになれる社会に 「子ども大学くまもと」理事長の宮津航一さん(21)【思い語って】
熊本日日新聞
-
「ゆりかご」など出自を知る権利検討会、3月21日に報告書公表へ 出自情報の保存や開示方法など
熊本日日新聞
-
「子ども大学」2年目の第1回講義、3月2日に崇城大で 「ゆりかご」の宮津さん理事長
熊本日日新聞
-
内密出産、法制化の課題探る 国会議員ら東京で勉強会
熊本日日新聞
-
「ゆりかご」など出自を知る権利検討会の報告書、25年3月に公表延期 「さらに議論深める」
熊本日日新聞
-
「内密出産」初事例から3年で計38件に 九州以外が6割超 熊本市の慈恵病院
熊本日日新聞
-
妊娠悩み相談は計2113件 熊本県や市、慈恵病院の24年度上半期 「思いがけない妊娠」が最多
熊本日日新聞
-
「ゆりかご」一定の匿名性を容認 熊本市の専門部会、慈恵病院の質問状に回答
熊本日日新聞
-
「ゆりかご」や内密出産の出自情報開示、18歳目安に検討 「知る権利」検討会が最終会合 12月末までに報告作成へ
熊本日日新聞
-
母親の情報開示を巡り議論 熊本市の慈恵病院で第10回検討会、年内にも報告書とりまとめ
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん
熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。