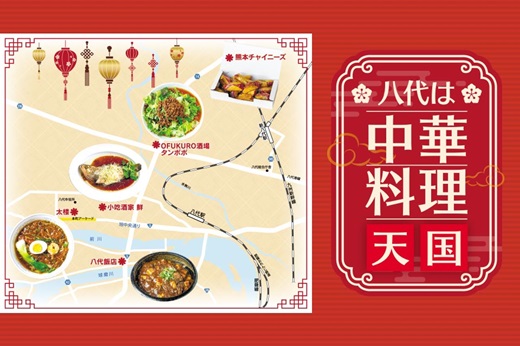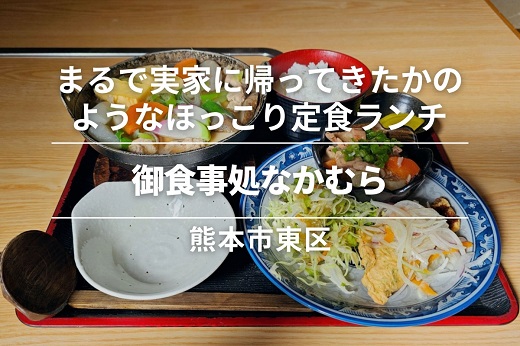【あの時何が 熊本市動植物園編②】猛獣舎確認「もし逃げ出していたら…」

「きょうはミルクを飲むペースが随分ゆっくりだな」。4月14日夜、熊本市動植物園の獣医師松本充史(44)は園内の飼育管理センターで、生後2週間のミミナガヤギにほ乳びんでミルクを与えていた。時計は午後9時を回り、帰宅が遅くなるのを覚悟していた。
長い耳を垂らし、黒っぽく小さな体が愛らしい。「フェリックス」と名付けられた雄の赤ちゃんは未熟児で生まれ、ようやく自力で立ち上がるようになったばかり。獣医師が交代で人工保育を続け、松本がこの日の当番だった。
「バタン」。他に誰もいないはずの室内に、背後のドアが閉まる音が響いた。不思議に思い振り返った瞬間、身動きすらできない激震に襲われた。とっさにフェリックスを抱きしめた。携帯電話が不快な警報音を発する。9時26分、熊本地震の前震だった。
停電はない。室外へ飛び出し、大きな余震でしゃがみ込む。階段を駆け降り、1階診察室のドアを開けると、白煙があふれ出した。「爆発する?」。後に手術用窒素ガスが漏れたと分かったが、その時は命の危険すら感じた。意を決して、煙の中を駆け抜けた。
ドアを開けると正門前広場。ほの暗い街灯が照らす風景は一変していた。地面から水が噴き出し、まるで川のように足元を流れる。異常発生を示す赤と青のパトランプが、あちこちで不気味に光る。
園には松本以外に2人の職員が残っていた。いずれも総務班の主任主事で、管理事務所2階で残業していた渡邉優(33)と兼坂明宏(41)だ。地震で事務所内の棚が倒れたが何とか無事。そろって屋外に出ると、約60メートル離れた動物管理センターから走ってきた松本と鉢合わせした。松本はフェリックスを抱いたままだった。
「猛獣を確認しなければ」。3人の思いは同じだった。だが、渡邉は4月に上下水道局から異動したばかり。動物の飼育には携わらない事務職で、2年目の兼坂も同じだ。そこに駆け付けた女性職員2人が合流。兼坂を事務所に残し、4人で猛獣舎へ急いだ。
夜の園内には、不気味な静けさが漂っていた。聞こえるのは地面から噴き上げる水の音や、遠くの鳥の鳴き声。動物に慣れた松本に比べ、渡邉の不安は大きかった。手には懐中電灯だけ。もし猛獣が逃げ出していたら…。
目の前に、竹ぼうきが立て掛けてあった。「このほうきでも持っていった方がいいかな」。振り返ると笑い話だが、その時の渡邉は真剣そのものだった。(岩下勉)=文中敬称略
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツTHEMES
熊本地震-
熊本地震で被災の熊本競輪場、2026年1月にグランドオープン 熊本市方針、駐車場整備の完了後
熊本日日新聞
-
【熊日30キロロード】熊本地震の被災を機に競技開始…32歳塚本(肥後銀行)が〝魂〟の完走 18位で敢闘賞
熊本日日新聞
-
天ぷら、スイーツ…「芋」づくし 産地の益城町で初のフェス
熊本日日新聞
-
地震で崩れた熊本城石垣、修復の担い手育成を 造園職人向けに研修会
熊本日日新聞
-
熊本地震で被災の油彩画、修復報告展 御船町出身・故田中憲一さんの18点 熊本県立美術館分館
熊本日日新聞
-
熊本城復旧などの進捗を確認 市歴史まちづくり協議会
熊本日日新聞
-
熊本市の魅力、海外メディアにアピール 東京・日本外国特派員協会で「熊本ナイト」 熊本城の復興や半導体集積
熊本日日新聞
-
熊本地震で被災…益城町が能登支える「芋フェス」 11日、NPOなど企画 能登の特産品販売、トークショーも
熊本日日新聞
-
「安全な車中泊」普及へ、熊本で産学官連携 避難者の実態把握、情報提供…双方向のアプリ開発へ
熊本日日新聞
-
石之室古墳、石棺修復へ作業場設置 熊本市の塚原古墳群 2027年度から復旧工事
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん
熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。