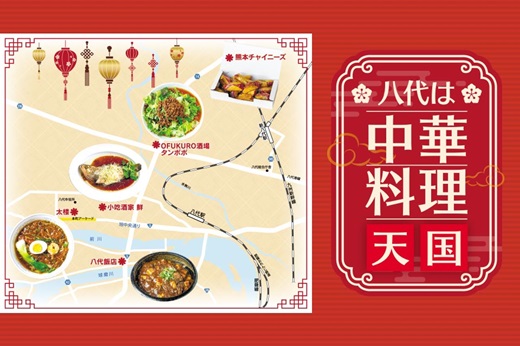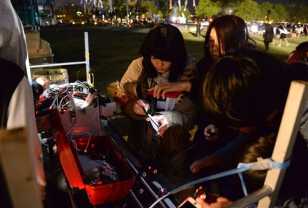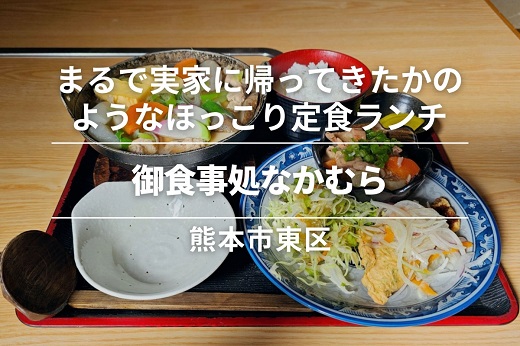【連鎖の衝撃 メディア編②】集団的過熱報道 大挙500人、行き過ぎ取材も

「家族と家を同時になくした状況で、何十人という記者から繰り返しつらいことを聞かれて。もう疲れ果てた」。益城町で母を亡くした女性は、憤りをあらわにする。
今回のような大災害や事故の際、取材が集中することで関係者に苦痛を与えたり、プライバシーを侵害したりする問題は、「メディアスクラム(集団的過熱報道)」と呼ばれ、度々指摘されてきた。熊本地震でも4月14日夜の前震後、全国から大挙してマスコミが押し寄せ、その数は1日で最大500人以上に膨れ上がったとみられる。
中でも、被害が甚大だった益城町や南阿蘇村周辺には取材が集中。マスコミの車両が交通の妨げになっているとの指摘があった。さらに上空を繰り返し旋回する報道ヘリ、朝から夜まで続く避難所中継、何十人もが取り囲んでの撮影や取材…。ネット上でも一部の報道のあり方が非難を浴びた。
繰り返されるメディアスクラムに報道側はどう対応してきたのか。2001年、全国の新聞や通信社130社が加盟する日本新聞協会や、205社の放送局でつくる日本民間放送連盟は▽嫌がる当事者への取材自粛▽住宅街などでの駐車や交通阻害への配慮-などの見解を策定。必要に応じて各地で報道責任者会議を開くことも決めた。
11年の東日本大震災では発生から1週間後、岩手県内の報道22社が緊急で協議。避難所や遺体安置所などでの節度ある取材などを申し合わせた。
熊本地震でピーク時に200人超を投入したNHKは各部署の代表を集めた会議を連日開催。「過去の経験を踏まえ、被災者の心情に配慮して取材にあたるよう現場への周知を徹底した」(熊本放送局)という。
しかし今回、被災者からの反発に際し、在京のメディアをはじめ、地元の記者クラブや報道責任者による調整はなされなかった。熊本日日新聞の丸野真司編集局長(59)は「中央メディアによるメディアスクラムであり、普段から住民と接している自分たちは違うという認識の甘さがあった。被災者の状況にもっと目を配り、地元紙として(会議などを)働き掛けるべきだった」と振り返る。
多くの震災取材を経験し、熊本にも前震直後から入った元TBS記者でジャーナリストの金平茂紀さん(62)は「ヘリの共同運用やテレビ機材・チーム編成などで工夫の余地はあったはずだ」とした上で、「災害報道では競争より被災地・被災者を重んじる姿勢が求められる。教訓を生かさない取材を続けていれば、視聴者や読者に見透かされてしまう」と自戒を込めて語る。
今回、現場記者の多くは悩みと迷いの中で被災者への取材を続けた。被災地の実情を発信することが、ボランティアや募金はもちろん、官民による支援策の充実につながるとの思いもあるからだ。
熊本地震後、岐阜県の実家に一時避難した熊本市の主婦小松美香さん(47)は、自らの体験を踏まえ、メディアへの期待を語る。
「県外では熊本地震のことが急速に忘れ去られている。支援を求める人がいることを発信し続けてほしい」(毛利聖一)
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツTHEMES
熊本地震-
熊本地震で被災の熊本競輪場、2026年1月にグランドオープン 熊本市方針、駐車場整備の完了後
熊本日日新聞
-
【熊日30キロロード】熊本地震の被災を機に競技開始…32歳塚本(肥後銀行)が〝魂〟の完走 18位で敢闘賞
熊本日日新聞
-
天ぷら、スイーツ…「芋」づくし 産地の益城町で初のフェス
熊本日日新聞
-
地震で崩れた熊本城石垣、修復の担い手育成を 造園職人向けに研修会
熊本日日新聞
-
熊本地震で被災の油彩画、修復報告展 御船町出身・故田中憲一さんの18点 熊本県立美術館分館
熊本日日新聞
-
熊本城復旧などの進捗を確認 市歴史まちづくり協議会
熊本日日新聞
-
熊本市の魅力、海外メディアにアピール 東京・日本外国特派員協会で「熊本ナイト」 熊本城の復興や半導体集積
熊本日日新聞
-
熊本地震で被災…益城町が能登支える「芋フェス」 11日、NPOなど企画 能登の特産品販売、トークショーも
熊本日日新聞
-
「安全な車中泊」普及へ、熊本で産学官連携 避難者の実態把握、情報提供…双方向のアプリ開発へ
熊本日日新聞
-
石之室古墳、石棺修復へ作業場設置 熊本市の塚原古墳群 2027年度から復旧工事
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん
熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。