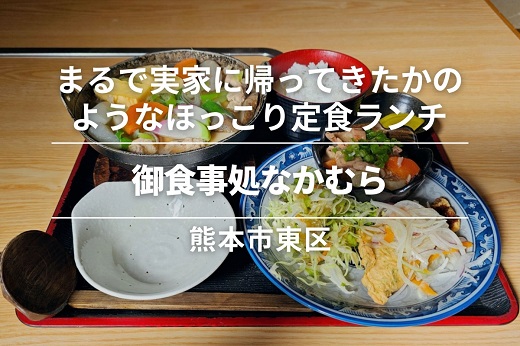カラフルな道路舗装、何でこの色に? 熊本県独自の統一基準 視覚的に注意喚起、安全守る

近年、よく目にするようになったカラフルな道路舗装。熊本県宇城市の元会社員の男性(67)が「SNSこちら編集局」(S編)に「従来の白塗りではなくカラー舗装を施すのには何か基準があるのでしょうか?」と写真とともに疑問を寄せた。 写っていた...
残り 1180字(全文 1300字)
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツNEWS LIST
熊本のニュース-
PFAS追加調査、目標値を下回る 宇城市の井戸24本 熊本県発表
熊本日日新聞
-
【菊池市議会】19日開会、新副議長に泉田氏
熊本日日新聞
-
宇土市の当初予算案、過去最大に 229億8千万円、教育費や民生費の増額目立つ
熊本日日新聞
-
おれんじ鉄道の橋、改修着工できず 地元漁協理事が漁業権と無関係な対応 鹿児島県・出水市が是正勧告
熊本日日新聞
-
木村熊本県知事、24日から台湾・高雄市訪問 航空会社訪れ市長会談
熊本日日新聞
-
鉱工業生産指数、2カ月ぶり低下 熊本県内の24年11月
熊本日日新聞
-
九州7県の銘酒とオリジナルおつまみ味わって 都内でPRイベント 熊本のメニューは?
熊本日日新聞
-
無免許事故で懲戒処分「妥当」 熊本地裁、公立多良木病院企業団課長の請求棄却
熊本日日新聞
-
【とぴっく・熊本市】全日本剣道連盟少年剣道教育奨励賞の伝達式
熊本日日新聞
-
荒尾市の一般会計予算案、過去最大に 4・2%増の274億7000万円 人件費や資材費が高騰
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん
熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。