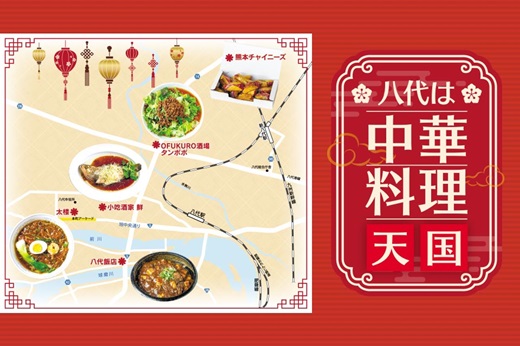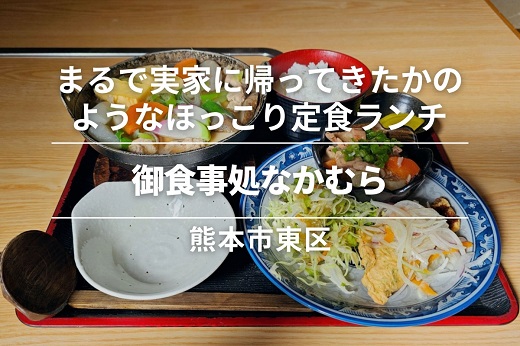やんちゃ坊主と論語 素読で培った教養 興味なければやる気起きず 「港町発展の条件」に出した答えは… <細川護熙さんエッセー>

子ども時代の私は結構やんちゃ坊主でした。戦争で一年疎開していたので、小学校に入学したのは敗戦の翌年、昭和二十一年です。疎開先だった鎌倉の家から地元の小学校、途中から横須賀にあるカトリック系の小学校に転校しました。父はそういうしつけの厳しい学校に入れた方がいいと考えたようです。
父は私たち兄弟に能とピアノの先生をつけましたが、草野球やチャンバラをしている方が楽しい年頃ですから、稽古のときはいつも逃げ回っていました。
ピアノの先生は髪をひっつめにした、いつも和服姿の中年の女性の先生でしたが、あるとき先生がトイレに入っているところを外から釘づけにしたため破門されて、ピアノはそれで中止になりました。
そんなありさまですから、当然ながら勉強も好きなわけはありません。その私が、いま古典や漢籍に親しんでいる原点は、幼年時代の素読にあったと思います。小学校に上がる前から「古文孝経」「論語」「万葉集」「古今和歌集」などの素読をやらされていたからです。
素読というのは、要するに音読です。内容の理解は抜きにして、古文や漢文の字面を追って声に出して読み、覚えるのです。明治の頃までは、みな素読で文章のスタイルを身体にしみこませ、それを基本素養として思想や哲学を培っていました。
小学生が「論語」の素読をしても意味はわからず面白いわけがないのですが、父が厳しく、戦時下で灯火管制が敷かれているさなかでも、押し入れや防空壕の中で、ロウソクを点[とも]しながら素読は続きました。できないと割り箸でピシッと手の甲を叩かれるので、半べそをかきながらやっていました。
「門前の小僧、習わぬ経を読む」ではありませんが、その頃覚えたものはいまもしっかりと脳裏に刻みこまれていて、何かの折に「論語」の言葉や「古今集」の歌などが口をついて出てきます。
父が漢文や古典の素読を子どもたちに叩きこもうとしたのは、京都帝国大学時代、恩師である哲学者の西田幾多郎先生の影響によるものだったそうです。
西田先生はあるとき父に「君は生死の関頭に立った時に何を思うか」と尋ねられました。父は「まだそのような経験がないのでわかりませんが、先生は何を思われますか」と逆に質問したのだそうです。すると先生は「子どもの頃に暗唱した古典だ。『十八史略』とか『論語』とかいったものだ」と言われた。そして「日本人はいま古典を読まないが、昔の人は古典を暗唱したものだ。四つか五つの時から『子のたまわく…』と覚えた。その時に意味はわかりっこない。しかしそれが生死の関頭に立った時にふっと頭に浮かぶのだ」「そこで人間が開ける。それが本当の教育というものだ」と言われて父はその教えを実践したわけです。
当時は父のやり方に反発していましたが、いまとなっては、教養の基礎を整えてくれたことに感謝しています。
中学は中高一貫のカトリック系の男子校に進みましたが、せっかく入ったこの学校は全く私の性に合いませんでした。教師はドイツ人の神父さんが多く、厳格な教育方針でした。バンカラな旧制高校的な雰囲気に憧れていた私としては、この校風はどうしても肌に合いませんでした。
私は自分が好きなこと、意味があると思ったことは一生懸命やるのですが、興味の持てないものは一切やる気が起きず、理数系、特に数学や物理、化学などには全く関心が湧きませんでした。宿題さえろくにやらなかったのでいつも落第点の赤点ばかり。通信簿を食堂の机の上に放り出すと、父はいつも苦虫を噛[か]み潰[つぶ]したような顔をしていました。
残り 960字(全文 2443字)
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツNEWS LIST
熊本のニュース-
水俣病患者、苦難の闘いつづる 関西訴訟原告の坂本さん没後3年 支援者が「続・水俣まんだら」出版
熊本日日新聞
-
【TSMCインパクト第2部「栄光再び 九州と半導体」③】人材育成、台湾と「相互連携で」 少子化で不足、教育機関にも動き
熊本日日新聞
-
【平成の大合併20年・まちとくらしの現在地 第2部「買い物環境」⑤】産山村中心部「うぶマート」が拠点施設に 三セク運営、公共交通でのアクセスに課題も
熊本日日新聞
-
南阿蘇村長に太田氏 現職の3選阻み初当選
熊本日日新聞
-
南阿蘇村議12人決まる 現職8人、新人4人
熊本日日新聞
-
6000人、干拓地駆ける 「玉名いだてん」「横島いちご」マラソン
熊本日日新聞
-
南小国町の役場窓口に「自動翻訳機」 外国出身住民の増加に対応 相談しやすい関係づくりを
熊本日日新聞
-
人道トンネルをアートで明るく 熊本市北区の清水小6年生 手をつなぐ人々を生き生きと描く
熊本日日新聞
-
24日初防衛戦の堤(九学高出)、〝兄弟子〟からエール ボクシング元世界王者・福原さん(熊本市)「重圧を力に。きっと勝つ」
熊本日日新聞
-
<バスケB2第23節・熊本92─60福島>ヴォルターズ田中、長距離砲でチーム最多18点
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん
熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。