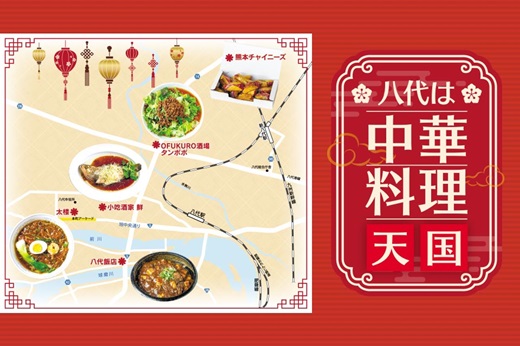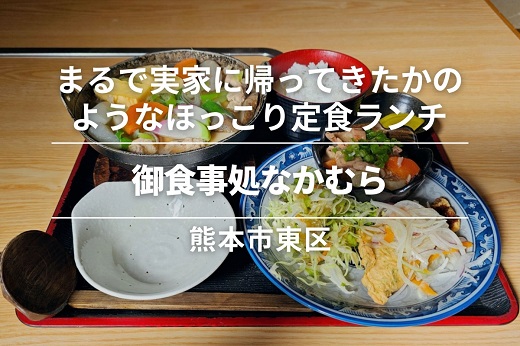【連鎖の衝撃 メディア編⑥完】神戸・東北の新聞と連携 被災者に勇気、思い共有

「仮設住宅で地震被災者が孤立しないポイントは?」。神戸新聞(神戸市)の報道部防災担当、阿部江利記者(33)が、被災者の中長期的な心のケアについて、兵庫教育大大学院教授に問い掛ける。
熊本地震発生直後の4月22日から同紙が始めた連載「阪神・淡路から熊本へ~提言」の取材場面だ。1995年の阪神大震災などを踏まえ活動する学識者や専門家らのアドバイスをまとめている。
この連載は5月9日から熊日夕刊に転載され、3カ月で21回になる。「阪神大震災時の経験を熊本の復興に役立ててもらいたい」と神戸新聞の面出[おもで]輝幸編集局長(58)。
関西に住む熊本ゆかりの人のメッセージを集めた同紙のもう一つの連載「こころ寄せて~熊本地震」も4月26日から熊日朝刊に転載している。これまでに14本を掲載。県出身のスポーツ選手や飲食店主らの温かい声が、熊本の被災者を勇気づけている。
初回に登場した神戸県人会長の乗富和夫さん(76)は「熊日に掲載後、友達から連絡があり、記事の切り抜きを郵送してくれた人もいて、私も温かい気持ちをもらった」と言う。
二つの連載の責任者、西海[にしうみ]恵都子報道部長(52)は「熊本地震の被害や被災者の思いを、神戸の読者と共感していくのが狙い」と話す。阪神大震災から21年たち当時の記憶が年々薄れていく。もう一人の防災担当、高田康夫記者(36)は「地元紙としてつなぎとめていく責任がある」と力説。2人は「地震を経験しなければ分からないこともある。被災地同士、連携を深めていきたい」と訴える。
一方、2011年の東日本大震災を経験した東北のブロック紙、河北新報(仙台市)からも読者投稿の転載の提案があった。4月21日からこれまで熊日の「読者ひろば」面に20本を掲載。「東日本大震災の時、全国の新聞社から読者投稿を頂き、ずいぶん励まされた」と同紙の担当者。
さらに熊日などに記事を配信する共同通信と全国の地方紙など計52社でつくるウェブサイト「47ニュース」では熊本地震の特設サイトを設置。熊日の記事を各紙のサイトで読めるようにした。「被災地の実情を全国に届けることができた」と熊日デジタルセンター。
記事や投稿だけでなく人的連携も。沖縄タイムス(那覇市)は、県警キャップの新崎[あらさき]哲史記者(36)を4月30日から2週間、熊日に派遣。“熊日記者”として被災地を取材し、連載「連鎖の衝撃 生命編」の1回分を執筆した。新崎記者は「生々しい現場を目の当たりにして『伝えたい』という気持ちがわいてきた」と話す。現在、共同通信も熊日に記者1人を、5月中旬から8月末までの予定で派遣している。
熊日は県内のテレビ・ラジオ5社とも連携。統一キャッチフレーズ「支えあおう熊本 いま心ひとつに」を朝夕刊1面に毎日掲載している。この言葉は、日本赤十字社のうちわや、玉名市の花火大会のサブタイトルに使われている。メディアの枠を超えた復興の合言葉になりつつあるようだ。(野田一春)=終わり
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツTHEMES
熊本地震-
熊本地震で被災の熊本競輪場、2026年1月にグランドオープン 熊本市方針、駐車場整備の完了後
熊本日日新聞
-
【熊日30キロロード】熊本地震の被災を機に競技開始…32歳塚本(肥後銀行)が〝魂〟の完走 18位で敢闘賞
熊本日日新聞
-
天ぷら、スイーツ…「芋」づくし 産地の益城町で初のフェス
熊本日日新聞
-
地震で崩れた熊本城石垣、修復の担い手育成を 造園職人向けに研修会
熊本日日新聞
-
熊本地震で被災の油彩画、修復報告展 御船町出身・故田中憲一さんの18点 熊本県立美術館分館
熊本日日新聞
-
熊本城復旧などの進捗を確認 市歴史まちづくり協議会
熊本日日新聞
-
熊本市の魅力、海外メディアにアピール 東京・日本外国特派員協会で「熊本ナイト」 熊本城の復興や半導体集積
熊本日日新聞
-
熊本地震で被災…益城町が能登支える「芋フェス」 11日、NPOなど企画 能登の特産品販売、トークショーも
熊本日日新聞
-
「安全な車中泊」普及へ、熊本で産学官連携 避難者の実態把握、情報提供…双方向のアプリ開発へ
熊本日日新聞
-
石之室古墳、石棺修復へ作業場設置 熊本市の塚原古墳群 2027年度から復旧工事
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん
熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。