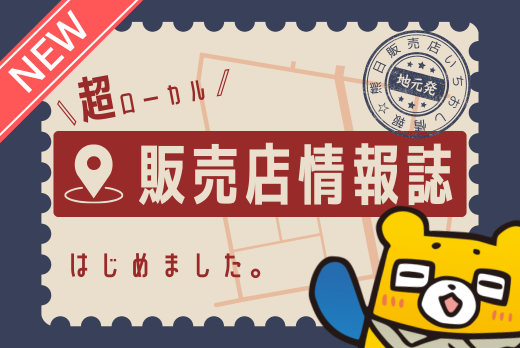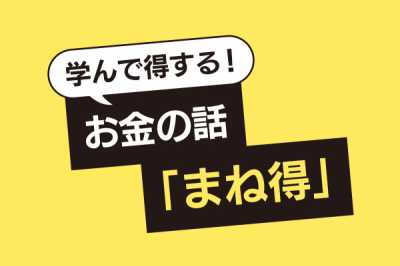【この人に聞く・熊本地震⑤】JVOAD事務局長の明城徹也さん 被災地の課題は? 「自主運営できる避難所に」

熊本地震の被災地で活躍するボランティア団体の調整役を担う「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD=ジェイボアード)」は、前震発生の翌日から熊本に入り、NPOや行政、社会福祉協議会などとの連携に取り組んできた。明城徹也事務局長に、ボランティアや支援の在り方を聞いた。(中村悠)
-JVOADはどのような経緯で設立されたのですか。
「2011年の東日本大震災では、いろいろな支援団体が全国各地から入ったが、動きがばらばらだった。行政や団体間でもっと連携が取れていれば、さらに効果的な支援ができたのではないか。そう考えたのがJVOAD設立のきっかけだ」
「さまざまな団体に呼び掛け、ことし6月の設立に向けて準備を進めていた最中に、熊本地震が起きた。本格的な活動は今回が初めて。各団体の自主性を重んじ、特徴を生かしながら力を発揮できる情報を提供したい」
-具体的な活動は。
「支援の重複や抜けがないよう、益城町など現地に入ったボランティア団体から細かいニーズや課題を聞き、情報を共有している。各団体が集まる『火の国会議』を毎日開いているほか、内閣府や県と頻繁に情報交換している。このため行政との連携はスムーズで、調整役の人員を効率的に配置できたと考えている。これまでに延べ200団体ほどが参加した」
-熊本地震の被災地が抱える課題は何でしょうか。
「一番の課題は避難所運営だ。行政だけで避難者のニーズにきめ細かく対応できないし、一方で罹災[りさい]証明書の発行など、役場の仕事も増えている。これからは、避難者の自立と避難所の自主運営が重要となる。被災者や避難所の状況は常に変わり、ニーズも変化している。行政の支援から漏れる被災者も出てくるだろう」
「そのときにボランティアが受け皿をつくれるかが鍵。東日本大震災では被災者から選ばれたリーダーが避難所を指揮したが、高齢者が多い熊本の避難所でうまくいくとは限らない。社会情勢を考え、どのような形が望ましいか考える必要がある」
-これからの支援に欠かせないものは何ですか。
「避難者の生活が仮設住宅に移れば、見守り体制や生きがいづくり、地域コミュニティーの問題などが重要になる。これまでは、民間の支援が益城町に集中したように感じるので、西原村や嘉島町、御船町などでもボランティア団体やNPO、NGO(非政府組織)をさらに受け入れやすい態勢を作ってもらいたい」
「過去の災害をきっかけに、市民活動が盛んではなかった所でも、町づくりのNPOなどが設立されたケースも多い。熊本でも地元主導で、住む人にとって良い環境をつくってほしい」
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツNEWS LIST
熊本のニュース-
「飲酒運転、起こさせない熊本を」 職員が事故死した熊本市が動画公開 忘年会など年末へ呼びかけ強化
熊本日日新聞
-
【水俣病関西訴訟 最高裁判決20年】行政の不作為立証した弁護団 「国と県は責任を果たして」 被害者救済、残る課題
熊本日日新聞
-
半導体教育で修学旅行を誘致 大津町の観光協会が今秋から 利用した高校生らにも好評
熊本日日新聞
-
【解説】安全不十分「計画通り」困難に 熊本市電の上下分離、25年4月移行見送り
熊本日日新聞
-
熊本市電「上下分離」延期「安全確保のため」 熊本市長が説明 25年4月移行予定を先送り
熊本日日新聞
-
厳選アクセサリーや雑貨で「日常に特別感を」 ヒロ・デザイン専門学校生 鶴屋にショップ、12月2日まで
熊本日日新聞
-
肥後銀行と福岡銀行が企業のSDGs支援で協力 各行のサービスを相互利用 肥後銀は25年1月めど
熊本日日新聞
-
新米味わい農家と消費者交流 「南小国町米フェス」 5品種を食べ比べ、晩秋の名物イベント
熊本日日新聞
-
親子で料理、会話も弾む 熊本市・山ノ内校区の子育てサークルで教室
熊本日日新聞
-
平和への思い沖縄の歌に託して 小国町の地域食堂でコンサート 沖縄三線グループ
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
学んで得する!お金の話「まね得」

お金に関する知識が生活防衛やより良い生活につながる時代。税金や年金、投資に新NISA、相続や保険などお金に関わる正しい知識を、しっかりした家計管理で安心して生活したい記者と一緒に、楽しく学んでいきましょう。
※次回は「家計管理」。11月25日(月)に更新予定です。