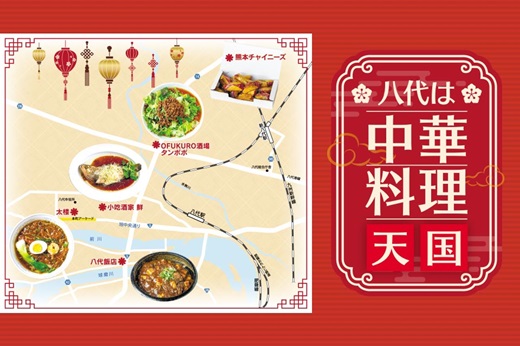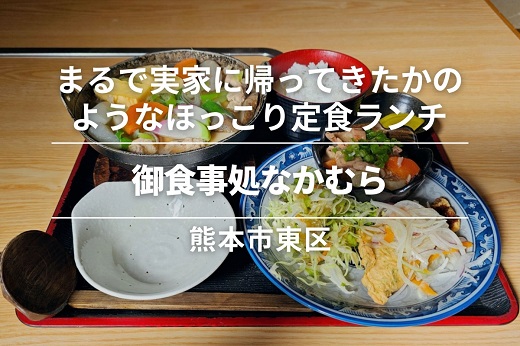宇土中・高「ウトウトタイム」導入10年 昼寝10分、授業中の居眠り減少 睡眠への意識変化も

熊本県立宇土中・高(宇土市)で昼休み後、10分間だけ昼寝をする「ウトウトタイム」を導入して10年。授業中に居眠りの回数が減少したり、自主的に睡眠をテーマに課題研究に取り組んだりと良い効果が出ている。横川修校長は「生徒の中で睡眠が大事だとい...
残り 996字(全文 1116字)
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツTHEMES
熊本の教育・子育て-
牛深高(天草市久玉町) 普通総合学科「自分だけの時間割」【くまもと高校図鑑】
熊本日日新聞
-
南稜高の2人が学校華道インターネット花展入賞
熊本日日新聞
-
表彰状に入賞作品を転写 山鹿法人会の絵はがきコンクール
熊本日日新聞
-
菊陽町の通学路 約60地点を改善
熊本日日新聞
-
【とぴっく・玉名市】韓国の高校生が専大熊本高訪問
熊本日日新聞
-
八代高生が熊本県産スギでベンチ製作 肥薩おれんじ鉄道や温泉施設に寄贈
熊本日日新聞
-
【とぴっく・八代市】イ草製品の売上げ金を贈呈
熊本日日新聞
-
熊本市の自転車用ヘルメット購入補助、中学生以下にも 上限2千円 25年度予算案に盛り込む
熊本日日新聞
-
270人出願変更 熊本県公立高入試 2025年度後期選抜
熊本日日新聞
-
菊池川流域の魅力や将来、熱く語る 玉名市で「高校生サミット」 8校40人が発表
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん
熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。