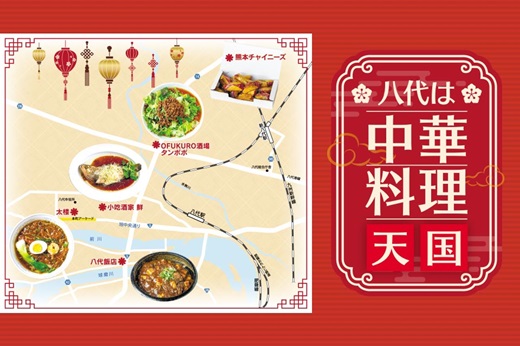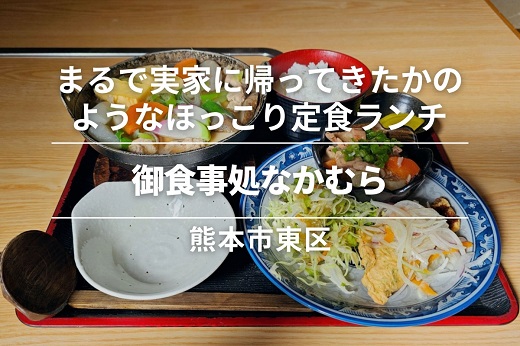江良水産(天草市) 雑節生産で「だし文化」下支え 新商品の開発も 【地元発・推しカンパニー】

天草市久玉町の工場が近づくと、もくもくと立ちのぼる煙が目に入り、天草のまきでいぶした魚の香ばしい香りに包まれる。牛深地域が日本一の生産量を誇る「雑節」の加工を手がけ、調味料メーカーなどに出荷、全国の飲食店や業務用の調味料として使われている...
残り 871字(全文 991字)
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツTHEMES
熊本の経済ニュース-
大学生と感じる農業のリアル 生産現場訪ねる活動、九州農政局の若手有志が企画
熊本日日新聞
-
妊婦支援で毎月米5キロ贈る 人吉市、東洋ライス(和歌山市)が無償提供
熊本日日新聞
-
【TSMCインパクト第2部「栄光再び 九州と半導体」②】各県に拠点分散の「九州方式」を サイエンスパークで訪台団一致
熊本日日新聞
-
ゆうちょ銀、熊本県と全45市町村に値上げ要請 公共料金の収納手数料 「事務コスト対応」数十倍の提示も
熊本日日新聞
-
【TSMCインパクト第2部「栄光再び 九州と半導体」①】「パイの奪い合いでなくパイを大きく」…波及効果23兆円、ライバル同士も結束
熊本日日新聞
-
半導体企業トップ「地域の特長生かした拠点を」 サイエンスパーク整備で認識一致 JASM社長ら
熊本日日新聞
-
半導体人材育成へ 産官学金が新協議会 木村知事「オール熊本で」
熊本日日新聞
-
1月の消費者物価指数、熊本市は3・7%上昇 県統計調査課
熊本日日新聞
-
熊本県内の研究者3人に奨励金 自然科学や医療分野 ウェルシーズ財団
熊本日日新聞
-
「やつしろ未来創造塾」 5期生が修了式
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
コロッケ「ものまね道」 わたしを語る

ものまね芸人・コロッケさん
熊本市出身。早回しの歌に乗せた形態模写やデフォルメの効いた顔まねでデビューして45年。声帯模写も身に付けてコンサートや座長公演、ドラマなど活躍の場は限りなく、「五木ロボ」といった唯一無二の芸を世に送り続ける“ものまね界のレジェンド”です。その芸の奥義と半生を「ものまね道」と題して語ります。