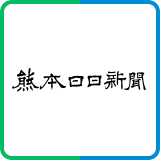【あの日から 阪神大震災30年】被災者高齢化、孤立や孤独死も 復興住宅、退去や死亡増える 「一人じゃない」思いが活力に 熊日記者ルポ

1995年1月17日、震度7の激震で神戸や淡路の街並みは崩れ、6400人以上の命が失われた。あの日から30年。阪神大震災を経験した人々はどう支え合い、教訓を語り継いできたのか。被災地を訪ね、熊本地震でも直面するであろう課題を考えた。(堀江利雅)
海岸を臨む一角にマンションが立ち並ぶ。神戸市中央区の災害公営住宅(復興住宅)「HAT神戸・脇の浜」。阪神大震災で家を失った人向けに建てられた。
集会所で、女性(75)と出会った。5キロ以上離れた兵庫区の自宅が全壊し、99年に入居したという。「最初はお互い知らない人ばかりで、集会や行事をたくさん開いていたんよ」と振り返った。
兵庫県内の復興住宅は最大時約4万2千戸が用意された。神戸新聞の調査では昨年末の入居者は計1万6416世帯で、うち被災者枠での入居は約3分の1にとどまり、全体の高齢化率は54・6%に上るという。
「ここ数年で亡くなったり、高齢者施設に入ったりする人が増えた。将来を考えると不安やね」。この女性の夫も2年前に他界した。
今年も「1・17」が近づく。「今も胸が痛む感じ。崩れた家や街の光景は覚えているし、30年間、苦労もたくさんしたなぁって」。しみじみと語った。

阪神大震災後、復興住宅で暮らす高齢者や震災で障害を負った人を支援してきた牧秀一さん(75)を訪ねた。震災直後に神戸市でNPO法人「よろず相談室」を立ち上げ、被災者に寄り添ってきた。
記者は熊本地震後の取材で、何度も助言をいただいた。30年たっても支援が必要な理由を聞いた。「震災がなければ家族や近所の付き合いがあったはずの高齢者が孤立し、時間がたつほど心身の状態の悪化や孤独死が増えるのが現実やね」
支援していた高齢者は最大時140人いたが、復興住宅から退去したり、亡くなったりして12人になった。NPOは2021年に解散し、個人で電話や手紙による交流を続けている。
「特別なことやないねん。『一人じゃない』と思えるだけで活力になるよ」。自身も75歳になり、つい先日、母をみとった。
「復興とか30年の節目とか、そうは考えられない人もおる。震災のせいでどうしようもなくなった寂しさは消えない」
記者は熊本地震を取材し「生活再建にはコミュニティーが欠かせない」と記事に書いてきた。でも、わが身を顧みると、熊本市の自宅近くにある復興住宅は取材で1度訪れたきり。「行政や地域の人々で寄り添い続けるしかない」という牧さんの言葉に30年の活動の重みを感じた。

地震後の課題には「記憶の風化」も挙げられる。神戸市中央区の「人と防災未来センター」は02年の開館以来、関連資料や証言を展示・紹介し、被災者の生活や街の復興の歩みを伝えてきた。
語り部の野村勝さん(86)が、長田区で復興まちづくりのリーダーを長年担った経験を話してくれた。「どこの街でも災害は起こり得る。被害の実相や復興の過程でどんな困難に直面するかを知っておくことも必要」と力を込めた。
センターは21年6月に展示を新設した。地震や豪雨、火山の噴火、津波などの災害を科学的に捉え、備えについて体験型の学習ができる。主任研究員の林田怜菜さん(40)は「一人一人の被災者や地域、行政などあらゆる立場から震災の記憶を読み解くことで、これからの防災を考えることにつながる」と説明する。
淡路市の北淡震災記念公園にも足を運んだ。阪神大震災で唯一、地表に現れた野島断層の一部を保存・展示している。1998年に開館し、全国の自治会や行政関係者の研修、修学旅行などで防災を学ぶ施設として注目された。だが、初年度に282万人を数えた来園者は次第に減り、2023年度は約13万人だった。
記憶の風化は、4月で発生9年を迎える熊本地震にも通じる課題だ。熊本では23年、熊本地震を起こした断層や被災した建物などを保存・展示する「震災ミュージアム」の拠点施設が開館した。
13日夜、宮崎県で日向灘を震源地とする震度5弱の地震が起きた。南海トラフ巨大地震への警戒も高まる中、「次への備え」は決して他人事ではない。
北淡震災記念公園で語り部を長年務めてきた総支配人の米山正幸さん(58)はこれからを見据える。「震災の記憶が遠のくにつれ、新たな災害への備えがおろそかになるのではないか。熊本など全国の被災地と連携した語り継ぎの活動も必要だ」
RECOMMEND
あなたにおすすめPICK UP
注目コンテンツTHEMES
防災くまもと-
平地でも大雪の恐れ 4~6日の県内、今冬一番の寒気 熊本地方気象台が警戒呼びかけ
熊本日日新聞
-
「弾道ミサイル飛来」想定、御船町で避難訓練 町民や小学生ら100人参加
熊本日日新聞
-
合志市・永江団地の50年振り返る 自治会が記念誌 写真や年表で紹介、ハザードマップも
熊本日日新聞
-
「山津波」から防災を学ぼう 1957年に玉名市で発生 体験者が天水中で講話
熊本日日新聞
-
錦町と少年院「人吉農芸学院」、災害時の相互協力協定 体育館などを避難所に
熊本日日新聞
-
【とぴっく・八代市】日奈久温泉神社で文化財防火訓練
熊本日日新聞
-
金峰山で初冠雪 熊本県内各地、寒い朝 南阿蘇村では休校も
熊本日日新聞
-
災害時の迅速な仮設住宅整備へ 熊本県とムービングハウス協会が協定 県産材も積極活用
熊本日日新聞
-
高森町に多目的広場「つくしまつもと」 車中避難所など災害時も活用
熊本日日新聞
-
熊本県内、28~29日大雪の恐れ 気象台が注意呼びかけ
熊本日日新聞
STORY
連載・企画-
移動の足を考える

熊本都市圏の住民の間には、慢性化している交通渋滞への不満が強くあります。台湾積体電路製造(TSMC)の菊陽町進出などでこの状況に拍車が掛かるとみられる中、「渋滞都市」から抜け出す取り組みが急務。その切り札とみられるのが公共交通機関の活性化です。連載企画「移動の足を考える」では、それぞれの交通機関の現状を紹介し、あるべき姿を模索します。
-
学んで得する!お金の話「まね得」

お金に関する知識が生活防衛やより良い生活につながる時代。税金や年金、投資に新NISA、相続や保険などお金に関わる正しい知識を、しっかりした家計管理で安心して生活したい記者と一緒に、楽しく学びましょう。
※この連載企画の更新は終了しました。1年間のご愛読、ありがとうございました。エフエム熊本のラジオ版「聴いて得する!お金の話『まね得』」は、引き続き放送中です。